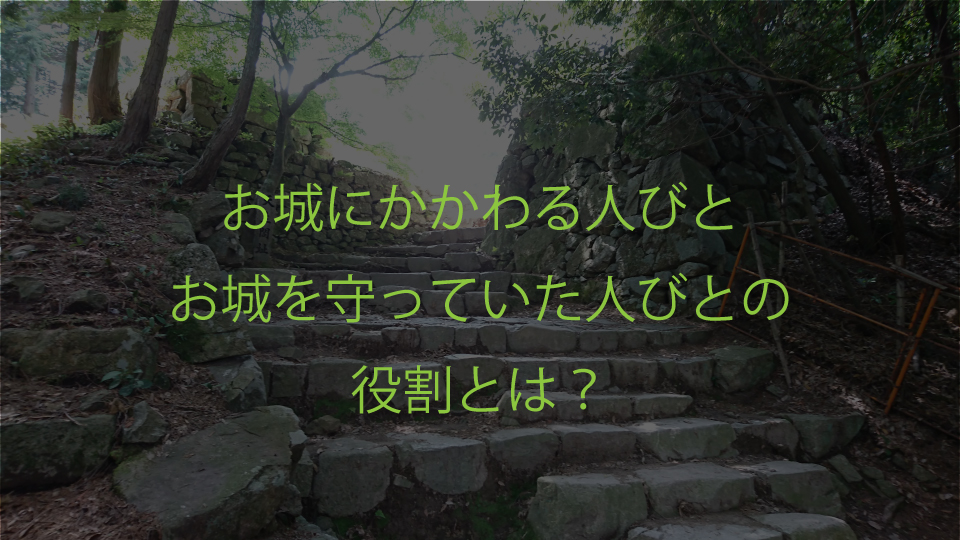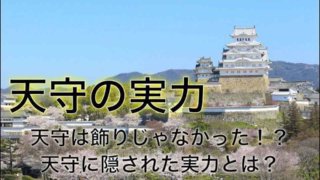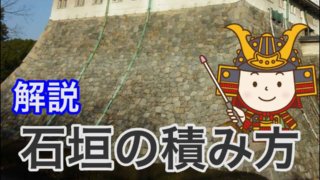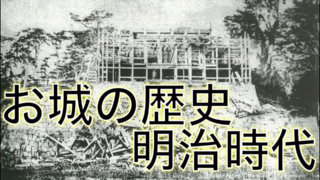今回は天守の象徴である「鯱(シャチ、シャチホコ)」について解説していきます。
「シャチホコ」といえば名古屋城天守の金のシャチホコが有名ですね!
最近、お城のブログを書いていてお城についていろいろ調べているうちに疑問が出てきました。
- そもそも「シャチホコ」って何?
- 誰が最初に「シャチホコ」をお城に使ったのか?
- 名古屋城天守の「シャチホコ」は金でできてるの?それとも金箔?
- 変わった「シャチホコ」について
Contents
そもそも「シャチホコ」って何?
みなさんに、質問です。
そもそも「シャチ・シャチホコ」ってどんな生き物ですか?
海にいるほ乳類のシャチではありませんよ。くれぐれもお間違えのないよう。
 シャチWikipediaより
シャチWikipediaより鯱(シャチ・シャチホコ)は魚へんに虎と書くんですけど、虎は関係ないんですね。
「シャチホコ」は頭は「龍」で、胴体が「魚」でできている空想上の生き物です。
 熊本城のシャチホコWikipediaより
熊本城のシャチホコWikipediaよりシャチホコは守り神とされていて、建物が火事の際には水を吹いて火を消すと言われてきました。
そのため、シャチホコは天守をはじめ、重要な櫓や門の上にも使われていました。
(次回、お城を見学するときには、天守以外に櫓や門の上にシャチホコがあるかどうか探してみてください。シャチホコがある櫓や門はそのお城にとって重要な建物になるので、どうしてその櫓や門が重要なのかを考えながら見学するのも楽しいですよ。)
シャチホコはお城に使われる以前はお寺の本堂に置かれている厨子(ずし、仏像などを入れておくための箱?みたいなもの、詳しくは「厨子」Wikipediaで)というものに使われていました。お寺に使われているシャチホコはみな木造で作られていました。
スポンサーリンク誰が最初に「シャチホコ」をお城に使ったのか?
「シャチホコ」はもともと仏教からきていて、建物を火事から守ってくれる空想上の生き物です。
では誰が最初にお城に使ったのか?それはズバリ
「織田信長」です。
お城における「シャチホコ」は織田信長の安土城天主が最初でした。
織田信長というと比叡山延暦寺を焼き討ちするなど神さまや仏さまを信じていない人のように勘違いされるけど、意外と天主にシャチホコを使うとか縁起を担ぐんですね。
しかも安土城のシャチホコは金箔を貼り付けた金シャチだったと言われています。
それまでお寺でしか使われてこなかったシャチホコをお城に使うだけじゃなく、シャチホコに金箔まで貼り付けてしまう信長の美的センスに当時の人たちは度肝を抜かれたことでしょう。
信長以降は、豊臣秀吉の大坂城や有力大名の広島城や岡山城なども金箔を貼った金シャチだったと言われています。
スポンサーリンク名古屋城天守の「シャチホコ」は金でできてるの?それとも金箔?
織田信長の安土城や豊臣秀吉の大坂城の「シャチホコ」は金箔を貼った「金シャチ」でした。
では「金シャチ」で一番有名な名古屋城天守の「シャチホコ」はどうでなんでしょう?金箔を貼り付けたものなんでしょうか?
名古屋城天守のシャチホコは金箔を貼り付けたものではありませんでした。
なんと金ののべ板を貼り付けたものでした。
名古屋城天守の金シャチ2体1対で純金換算「約215kg」(2018年7月2日の金相場1g−4864円で計算すると、10億4476万円!)という、大量の金を使っていました。
江戸時代、名古屋を治めていた尾張藩は財政が苦しくなると金シャチから金を取ってきて財政再建に使ったとされていますし、明治以降にも夜な夜な名古屋城天守に登って金シャチから金を盗ろうとして逮捕された人が何人もいました。
スポンサーリンク一風変わった「シャチホコ」
ふつう「シャチホコ」は2体で1対ですよね。
だけど新潟県新発田市にある新発田城には一風変わったシャチホコがあります。
何が変わっているかというと1つの建物にシャチホコが3体ものっているんです。
この御三階櫓は櫓と言っているけど新発田城にとっては実質的な天守で、築城当時、江戸幕府に遠慮して「これは天守ではないですよ、櫓ですよ!」と言って建てたものでした。
ではなぜ御三階櫓にシャチホコが3つもあるのか?
説はいろいろありますが、「敵が攻めてきたときにシャチホコが3つあることでお城の向きを誤解させる意図があった」とか!
ちなみに3体のシャチホコのうち、2体がオスで、残り1体がメスです。見分け方はオスにはキバが片側3本あって、メスは2本です。
あとシャチホコの素材では瓦製が一般的ですが、松江城は銅板で作られていますし、高知城、宇和島城には鋳造の青銅製のシャチホコが作られました。